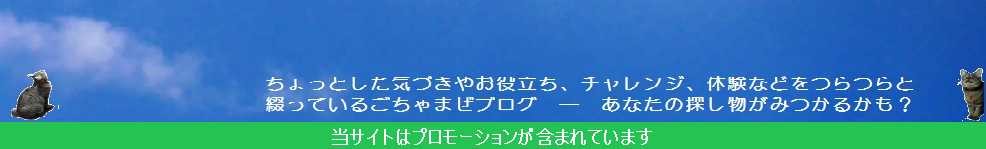除夜の鐘をききながら、年越しそばをいただき、新年になると家族で近くの神社に初詣に行っていました。
毎年当たり前のように、行き、行く日はほぼ元旦でしたが、時間はまちまち。
たいそう並んで寒さに震えた経験から、翌年は時間帯を変更・・
というように、お参りすることだけが目的のいわば、よく知らないけど行く。
みたいな決まり事のようになっています。
初詣って本当はどんな意味や由来があるのかしらとか、行く日にちや時間に決まりはあるのかという疑問がむくむくと・・・
スポンサーリンク
初詣とはなんぞ?その意味は
初詣は初詣(初参り)ともいい、年が明けてから、
その年はじめて神社仏閣などへ参拝する行事のことですね。
猫にゃん
お参りって何するんだにゃん
招猫ニャン
一年の感謝を捧げたり、新年の無病息災や平安無事を祈願したりしますね。
波空
お参りをする以外にも、絵馬に願い事を書いたり、御守りやおみくじなんかを買ったり・・・境内で甘酒や神酒を頂いて厄除けしたり。
屋台が出る所もあるし、そういう催しとしても知られているかな。
屋台が出る所もあるし、そういう催しとしても知られているかな。
猫にゃん
甘酒!飲みたいにゃん。屋台もいいにゃぁ。初詣、行く行く!(^o^)
波空
・・・(^^;)
まだ時計がないころ、日が暮れると一日の終わりで、日が暮れた夕方からが次の一日の始まりとされていました。
なので、昔は、大晦日の夕方からがお正月だったんですね。
その大晦日から元旦の朝にかけて、家長がその土地の氏神様を祀った神社に泊まり込み、夜通しその年の豊作や家内安全などを祈願する「年籠り(としごもり)」をしました。
この年籠りが大晦日の夜に詣でる「除夜詣」と元日に詣でる「元日詣」に分かれ、この元日詣が初詣の原型となったとされています。
猫にゃん
ん?お正月の神様って年神さまじゃなかったっけ?
波空
うん、お正月に各家に毎年やってくる神様は年神さまだね。氏神様は同じ地域に住む人々の共通の神道の神様のことで家にはこないのね。
猫にゃん
神様っていっぱいいるのか・・・
スポンサーリンク
初詣の始まり
波空
初詣の文化って明治時代に始まったそうなのね
猫にゃん
へえ、もっと昔からある行事だと思ってたけど・・・意外と新しいんだにゃ
波空
明治18年に国鉄(JR)が日本で初めての鉄道を開通させ、汽車を走らせたのが広まったきっかけなんですね。
初めて初詣という言葉が出てきたのがこの頃で、一般的になったのは大正時代と云われています。当時は汽車に乗るのが夢、みたいな時代だから、せっかく汽車に乗るのなら有名な川崎大師にお詣りに行こうとなったそうで、それが話題となり参拝客も増え続け、それが全国の神社に広まったということのようですよ。
初めて初詣という言葉が出てきたのがこの頃で、一般的になったのは大正時代と云われています。当時は汽車に乗るのが夢、みたいな時代だから、せっかく汽車に乗るのなら有名な川崎大師にお詣りに行こうとなったそうで、それが話題となり参拝客も増え続け、それが全国の神社に広まったということのようですよ。
猫にゃん
初詣が広まったのは鉄道のせいとかって、今では考えられないにゃ。それまでの日本人は新年に何をしていたのかにゃ?
波空
年神さまを迎え入れ、おもてなしにお節料理を作ったり、年神さま中心に新年の文化があったそうなのね。
基本家にこもっていた、今のにゃんと同じね。(^^)神社へのお参りも自分の住むところから恵方の方角にある神社にお詣りするのが(恵方詣り)伝統という・・・
基本家にこもっていた、今のにゃんと同じね。(^^)神社へのお参りも自分の住むところから恵方の方角にある神社にお詣りするのが(恵方詣り)伝統という・・・
猫にゃん
なるほど、交通の便がよくなったことで、遠くの有名な神社にも行けるようになったということなんだにゃ
波空
交通の便がよくなっただけでなく、各鉄道会社の宣伝合戦もあるんですね。
各社が沿線の神社仏閣を恵方であると宣伝して、恵方詣りの本来の意味がなくなり、みんな自由に好きな社寺をお詣りするようになったということのようです。
それに、国鉄と京成鉄道が顧客獲得競争で、大晦日の深夜に電車を走らせるという行為にでたのがきっかけで、大晦日から参拝に行けるようになったというのも大きな要因になってますよね。
各社が沿線の神社仏閣を恵方であると宣伝して、恵方詣りの本来の意味がなくなり、みんな自由に好きな社寺をお詣りするようになったということのようです。
それに、国鉄と京成鉄道が顧客獲得競争で、大晦日の深夜に電車を走らせるという行為にでたのがきっかけで、大晦日から参拝に行けるようになったというのも大きな要因になってますよね。
猫にゃん
でも、鉄道とかない頃でも「お伊勢参り」なんていうのがあったよね?みんな歩いて行ったんだよね?
波空
そうだね。明治以前はお正月って家族揃って自宅で迎えるものだったけど、明治から大正にかけてみんなが初詣にでかけるようになった背景には、江戸時代に大流行したお伊勢参りがあったから、と云われているね。
猫にゃん
お伊勢参りってすごいことなの?
波空
昔は関所ってあったでしょ?それがなくなってから庶民でも徒歩で自由に旅ができるようになったのね。
で、その頃『伊勢神宮』は「御師(おんし)」という役割の人々を全国に派遣して、ご利益や由緒を説いたという・・いわゆる宣伝活動ですね。
街道の整備も進み旅ができる世の中になりつつあったから、その目的地として伊勢神宮への参拝が好まれたということです。
親しい人たちと一緒に、同じ目的で旅をするという・・お伊勢参りのスタイルが根付いていたからこそ、初詣という新しい習慣も自然と広まっていたと考えられているようです。
で、その頃『伊勢神宮』は「御師(おんし)」という役割の人々を全国に派遣して、ご利益や由緒を説いたという・・いわゆる宣伝活動ですね。
街道の整備も進み旅ができる世の中になりつつあったから、その目的地として伊勢神宮への参拝が好まれたということです。
親しい人たちと一緒に、同じ目的で旅をするという・・お伊勢参りのスタイルが根付いていたからこそ、初詣という新しい習慣も自然と広まっていたと考えられているようです。
初詣にいくならいつ?
波空
初詣はいくの?
猫にゃん
行きますにゃん。でも夜中は寒いから、年が明けてからひと眠りして、お雑煮とか食べてから行くにゃん。
波空
そうなのか・・私はいつも、年が明けたらすぐ出かけてるかな・・1:00頃とか
猫にゃん
初詣に行く日にちや時間に決まりってあるのかにゃん?
波空
初詣には、定められた規定は特に無いみたいね。年明け最初の参拝を初詣としていて、年内ならいつ参拝に行っても、その参拝が年内最初の参拝であれば「初詣」となる場合もある・・・と『デジタル大辞泉』の定義にありますね。
猫にゃん
ほぇ・・そうなの?いつでもいいのかぁ・・・
波空
一般的には、正月三が日に参拝するのを初詣といっているけど、1月中の参拝も初詣とする考え方もありますね。松の内の7日までとか、小正月の15日までとか・・・いろいろですねぇ。回数にも制限はないみたいだね。
猫にゃん
ふむ。でも神社の雰囲気っていうの?いつでもいいって言っても、3が日とかじゃないと、あんまりお正月という感じがなくならないかにゃ?・・・
波空
そうだよね(^^;。初詣に行っても、閑散としていたらなんかね・・・やっぱり、みんなが行く時期に合わせて、その中でも自分の都合にあった時に行けばいいんじゃない?にゃんなら甘酒が振る舞われる内だね(^^;
猫にゃん
ふむ。やっぱり元日に行こう(^^)・・・

波空
初詣の目的は甘酒じゃなくて参拝なんだけどね・・・正しい参拝のしかたも覚えようね(^^;
初詣とは さいごに
初詣という行事が意外と最近?からというのや広がったいきさつがちょっと驚きでしたが(^o^)
まぁ、だから行かないではなくて、いつもお正月は家でぐでーとしてるだけだし、今まで通り近くの神社に感謝と今年の祈願に出かけるくらいはしてみたいと思いました(^^)