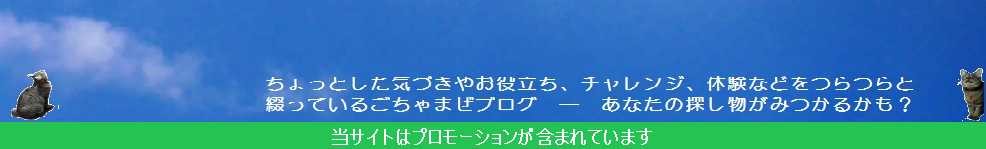大晦日になると毎年年越しそばなんぞ食べながら、「あ、なった」と家族と1年の終わりをしみじみ思うのですが・・
その除夜の鐘って年越しの頃になるのが当たり前になってきてるけど起源てなんなんだろう?
とか、108回なるのを誰がどうやって数えているのか?
またいつの間にか聞こえてきて、気が付けばいくつめの鐘かはわからないけど、本来何時に打ち始めて何時までなのか?とか・・どうにも気になります。
スポンサーリンク
除夜の鐘の起源と意味
波空
除夜の鐘って、1年のしめくくりって感じがするよね
猫にゃん
大晦日に鳴る鐘はなんで除夜の鐘っていうの?
波空
除夜の鐘の「除」には古いものを捨てて、新しいものを迎えるという意味があるのよね。1年が終わって、新しい年を迎えるその年の終わりの夜、つまり除夜とは12月31日の大晦日の夜ということになるんだよね。
そして、大晦日になるとお寺で撞かれる鐘が除夜の鐘ということですね。
そして、大晦日になるとお寺で撞かれる鐘が除夜の鐘ということですね。
除夜の鐘の起源は、詳しく分かっていませんが、中国の宋(960~1279年)に起源があり、鎌倉時代に禅寺に伝わったといわれています。
鎌倉時代は現在の仏教が確立した時、武家政権の始まりの時代です。
それに合わせて仏教も大きく進歩し新宗派も出来ました。
新しい宗派は、人々に新しい寺の存在を知らせ、信仰を増やすための布教活動が必要だったわけで、除夜の鐘はその布教活動の一つだったのですね。
鎌倉時代は現在の仏教が確立した時、武家政権の始まりの時代です。
それに合わせて仏教も大きく進歩し新宗派も出来ました。
新しい宗派は、人々に新しい寺の存在を知らせ、信仰を増やすための布教活動が必要だったわけで、除夜の鐘はその布教活動の一つだったのですね。
仏教では修行を積むことで煩悩を祓い解脱し、悟りを開くことができるとされています。
鐘の音は仏の声や仏の教えとして、厳しい修行を積んでいない私たちでも、その鐘の音を聞くことで、この1年の罪を懺悔し、煩悩を除き、清らかな心になって新しい年を迎えるという信仰が伝わりました。
なので、新年を迎える時に鐘を打つのですね。
除夜の鐘は、そんな行事です。
除夜の鐘は本当に108回?どうやって数えているの?
波空
除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれるけど、この「108」という数の由来には、諸説あるんだよね。
一般には煩悩説が有名だね。
一般には煩悩説が有名だね。
猫にゃん
うむ。煩悩の数が108回というのは昔からきいてるような・・
波空
煩悩の108というのは人間の眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)のそれぞれに好(こう:気持ちが好い)・悪(あく:気持ちが悪い)・平(へい:どうでもよい)というのがあって「6×3」で18。この18類それぞれに浄(じょう)・染(せん:きたない)の2類があって36類、この36類を前世・今世・来世の三世に配当して108。
これが人間の煩悩の数を表すと云われているよ。
これが人間の煩悩の数を表すと云われているよ。
猫にゃん
他の意味もあるの?
波空
1年間の月の数の12、二十四節気の数の24、七十二候の数の72を足した数が108ということで1年間を表す数というのもあるね。他にも「四苦八苦」ということばから、4×9+8×9=108という説明もあります。
猫にゃん
なんだか無理やり理屈つけてるみたいだにゃあ。
波空
お寺によって撞く回数は108回とは限らず、200以上の場合もあるそうよ。要するに、108というのは、数字自体の意味より「大変多い」ということを表しているのよね。
猫にゃん
それにしても、お寺では108回って、どうやって数えているのかにゃ?
律儀に僧侶が指折ったり、正の字書いたりしてるのかにゃw。
律儀に僧侶が指折ったり、正の字書いたりしてるのかにゃw。
波空
お寺によっていろいろ工夫してるみたいだね。
整理券を配るところでは、その数を108までにしてるとか、カチカチって時計みたいな数を数えるやつね。カウンターで数えているところもあるようだよ。
整理券を配るところでは、その数を108までにしてるとか、カチカチって時計みたいな数を数えるやつね。カウンターで数えているところもあるようだよ。
猫にゃん
へえ、ちゃんと数えているんだ
波空
他にもひもに通した、番号の入った108枚の札を一枚ずつめくっていくというのもあるようです。お寺ごとにいろんな数え方があるようですよ。
猫にゃん
でもすごく多いっていうことで108にこだわらないお寺もあるんだよね?
波空
鐘をつくことができるお寺で「お参りに来ていただいた方は何回でもついていただけます」と回数にこだわらないで、参拝する人の気持ち優先というのもあるよね。
猫にゃん
ふむ。今年は数えてみようかな、なんて思ってたけど(^^; 数にこだわることはないのだにゃ
スポンサーリンク
除夜の鐘の鳴り始めなり終わりの時刻は?
波空
年越しそばを食べながら除夜の鐘の音がきこえてくると、ああ、今年も終わりだなとしみじみ思うよ。
猫にゃん
除夜の鐘って気がつくと、いつのまにか鳴っている感じがするけど、いつ鳴り始めるとか決まりがあるのかな?
波空
多くのお寺では23:00頃から撞き始めるみたいね。除夜の鐘は、大晦日から深夜0時を挟んで撞かれるんですね。107回までを旧年中に、最後の1回は新年になってから鳴らすのが正式な決まりだそうよ。
猫にゃん
なんで?
波空
最後の1回は、新しい1年を煩悩に悩まされないようにという願いを込めるためだそうです。煩悩を旧年中に払ってしまい、新しい年は清らかな身で迎えようということですね。きちんと24時に終了するという寺院では、つき始めを早めに22:00頃からに設定しているところもあるよ。
猫にゃん
ところで鐘をつかせてくれる寺院もあるってきいたような・・
波空
そうだね。大半の寺院は、無料で撞くことができるみたいだけど、お寺によってまちまちで、108回しか鳴らさないので、先着順で締めきるところや希望者全てに鳴らしてもらうので108回より多くつくところもあるみたい。
猫にゃん
除夜の鐘ついてみようかな。
波空
鐘をついてみたいと思っているなら、少し早めに、出かけたほうがいいかもね。有名な寺院では、整理券を配布したり、有料になるとこもあるみたい。
猫にゃん
そうなのか~事前にお寺にきいておいた方がいいんだにゃ
除夜の鐘のまとめ
何気なく年越しの時にきいていた鐘も意味がわかってくると、また新たな気持ちで耳に届きそうです。
鐘の音を聞きながら、煩悩が1つ消えた、2つ消えた・・なんて思いながらお蕎麦を食べるのもいいかも(^^;
それにしても、今一つ煩悩のことが?なので、次回はそのことについてまとめます。