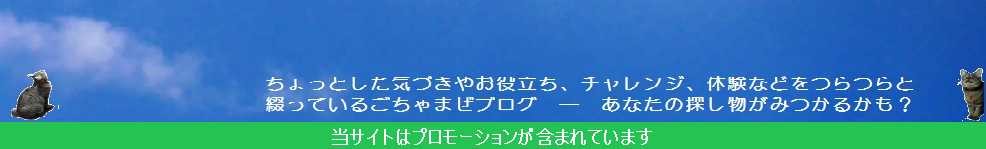8月のお盆の時期になると、どこからともなく太鼓の音が聞こえてきて、
何となく夏も終わりに近づいたかなー、なんてしんみりしますね。
いや、まだまだこの先も、めっちゃ暑い日が続くんですけどね
そんな夏の風物詩のひとつが 盆踊り。
盆踊りをする意味
盆踊りって、子供の頃から当たり前にあるけれど・・・
そもそもなんのために踊っているんでしょう?
櫓のまわりをぐるぐる回りながら、誰でも参加できて、楽しめる・・
盆踊りの意味としては、村落社会においての娯楽と村の結束を強める役目を果たしていたということなんですね・・
お盆の時期に行なわれますが、宗教的意味合いは薄く、いわゆる農村や庶民の娯楽として楽しまれてきたということです。
でも、始まりはいつ頃なんでしょうか?
どんないわれがあるのでしょうか?
夏の自由研究にもなるかもしれませんね(^^
盆踊りについて調べてみました♪
盆踊りの由来とは?

盆踊りは本来、お盆に帰ってきた先祖の霊を迎えるための念仏踊りが始まりの宗教行事だという説と、歌垣(男女が交互に求愛の歌を掛け合う習俗)からの流れの行事だという説。
また原始進行の儀式だったという説など諸説あります。
縁日でも見かけるお面、
あれが盆踊りの時に使う重要な小道具だった地方もあります。
身分に関係なく誰もが参加できる祭りだったため、その顔を隠す、
という役目と言われていたり、あの世から帰ってきた霊に、顔を見せないためだったとも言います。
それが、月日が経つうちに人気キャラクターをモチーフにしたものになってしまうんだから、面白いですよね。
日本だけではなく、日本人移住者が多い国でも盆踊りは行われています。
ハワイや南米、アメリカなどでは毎年たくさんの人が集まって盛り上がりを見せています。
マレーシアの盆踊り。
5万人規模だそうです。
ちょっとした音楽フェスのような雰囲気ですね?
やっているのは盆踊りなんですけど。
動画をみつけたので貼らせていただきました
いつからあるの?盆踊りの起源はどこから?
これもまた色々な説がありますが、文献に盆踊りが登場するのが室町時代です。
平安時代に始まった踊り念仏が民間習俗と習合して念仏踊りとなり、盂蘭盆会の行事として定着したとの考え方が濃厚</span >です。
その頃は初盆の家に踊り手が訪ねていって、家の前で輪になって踊ったそうですよ。
もう現代の盆踊りの原型は完成していたということですね!
踊り念仏は鎌倉時代には全国に広まっていましたが、それはかなり激しいものだったようですね。
念仏によって魂が救済されるということが僧侶たちを熱狂させたようで、それはそれは激しく踊りまくったそうなんです。
そんなこともあって、踊り念仏は大ブームになったそうです。
日本人は人前で踊るということに、慣れていない民族なのかと思っていましたが、そんなこともなかったんですね?
そしてその盛り上がりは江戸時代には絶頂になります。
江戸では7月に始まった盆踊りを連日連夜踊り続け、10月まで続いたこともあったそうです。
次第に盆踊りは未婚の男女の出会いの場になってきたようです。
さらには既婚の男女のアバンチュールの場所になることも少なくはなかったそうですよ!
明治の時代には風紀を乱すという理由で取り締まりも行われたというのですから相当ですねー。
現代では民間のお祭り的な意味合いが大きくなっているせいか、民謡的な音楽ももちろんありますが、アニメやJポップをアレンジした音楽で踊る様子も見られます。
縁日や屋台が多くでるお祭りもあり、仮装などのイベントで盛り上がる盆踊りもめずらしくありませんね
盆踊り 最後に
現在の盆踊り、本来の意味からは少し外れてきてしまっているのかもしれませんが、日本の夏を彩るイベントですから、ずっと続いてほしいものですね!
歌や踊りって、知らない人どうしでもなんだか一緒に踊ることで、共感が生まれたりしますよね(^^)