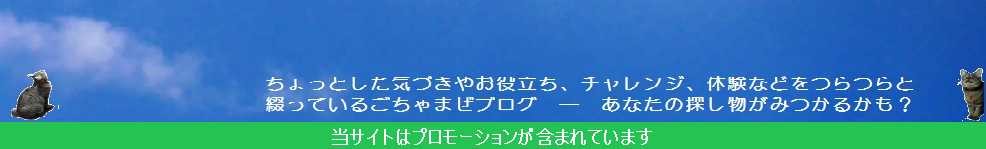3月の祝日には春分の日があります。
この日は春彼岸の中日。
日本では春と秋に2回、このお彼岸というのがあります。
お彼岸とは?本来の意味と何をするのか?お墓参りに行っているけど、今回はいけない
・・・いかないと罰が当たる?そんなこと思っている人もいますよね?
春彼岸の意味
「彼岸」はサンスクリット語の「波羅密多」から来たものといわれ、煩悩と迷いの世界である此岸(しがん)にある者が、「六波羅蜜」(ろくはらみつ)の修行をする事で悟りの世界すなわち彼岸(ひがん)の境地へ到達することが出来るというものです。
なんだか難しいですね。
現世の私たちは煩悩の中にあって、極楽浄土にいくためには悟りの境地へ達しないといけない・・・と
そのためには「六波羅蜜」というのがあり、これは彼岸へ行くために行う修業のこと。
・布施(ほどこすこと)
・持戒(つつしむこと)
・忍辱(しのぶこと)
・精進(はげむこと)
・禅定(精神を集中すること)
・智慧(真理をみきわめる力)
この六つの修行徳目と言うことになります。

春分の日には、太陽が真東から上がって、真西に沈み昼と夜の長さがほぼ同じになります。
この日を挟んだ前後3日の計7日間を「彼岸」と呼びます。
この時には此岸(しがん―この世)と「彼岸」(ひがん―あの世)が最も近づく期間で、その時に功徳をすることで極楽浄土へいくことができると考えられたんですね。
六波羅蜜を一度にすることは難しいので、1日に1つ6日かけてやりましょう、
そして中一日、春分の日には先祖の霊を敬い感謝する日として、お墓参りをしましょう
・・・ということになるのかと思います。
春彼岸には何をする?
国民の祝日になっている春分の日、この日は春彼岸の中日にあたります。
ちなみにお彼岸というのは毎年同じ日ではなく、天文的に1~2日のずれがあります。
今年の春分の日はいつ?
お彼岸はいつからいつまで?という疑問も毎年ききます。
近年の春のお彼岸の日にちは次のようになります
2023年 3月18日 3月21日(火) 3月24日
2024年 3月17日 3月20日(水) 3月23日
2025年 3月17日 3月20日(木) 3月23日
地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定しての計算予想です。
ただし、地球の運行状態は常に変化しているために、将来観測した結果が必ずしもこの計算結果のとおりになるとは限りません(国立天文台より)
春の彼岸の場合は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」という趣旨があるようです
お彼岸=お墓参りというように思われているように感じます。
お彼岸にすることといえば、
一般的には、お彼岸にはお墓参りをして、お墓の掃除や供花やお供えをし、家族で牡丹餅をいただくとなります。
また、祝日の趣旨で言えば、自然に感謝し、生き物を大切にするとなります。
お墓参りに行けないと罰が当たる?
お墓参りにいかれる方も多いと思いますが、これはお彼岸にはお墓参りしなければいけない、というわけではありません。
でも、いつもお参りしている方、あるいはお墓参りするものだと思っている方にとっては、
これはいけないことだ・・申し訳ないというような気持になりますよね。
なので、お墓参りができなかった時に、なにか悪いことがおこるのではとか、罰が当たるのではないかという思いがわくのではないかと思います。
でも、お彼岸にお墓参りをするという慣習はあっても、ルールとか決まりではないのです。
お墓になくなった方がいるわけではないのです。
先祖を大切にしましょうということで、お墓に納めた先祖を敬い、お墓をきれいにしたり、お参りしたりしますが、別にお彼岸でなくてもいいわけです。
なんとなく行く日、みたいなものがないと、行かないという方にはいい目安になると思います。
でも仕事やいろいろな都合でこの期間に行けないならば、他の行ける日に行けばいいのです。
毎日行ってもいいんですね(^^)

お墓は、生きている者のためにあるのだと思います。
供養をすることで自分の心の平安や、形にできない先祖供養をお墓参りなどで形にしているのではないでしょうか
私は死んだ経験がないので(^^;
死んだ人がどこに行って、現世とどうかかわるのかはわかりませんが、先祖からみたら、私たちは子孫なわけで、そこに良い悪いを決めて罰を当てるというのは無いと思います。
というか、それが可能なら、世の中罰があたってばかりいる人であふれるのではないですか?
罰が当たったということは、その人の心の持ちようではないでしょうか?
何か悪いことがおきたり、続いたりしたとき、気持ちの中にお参りに行っていなかったというのがあれば、「この前お墓参りにいけなかったせいだ」となるわけです。
でも、お参りに行っていても起こることはおこるわけです。
何かあれば理由をつけたいのは誰でもあると思います。
良いにつけ悪いにつけ。
そこはお墓参りと切り離して、先祖供養やお墓参りは、できるときにしっかりやることで、物事の良し悪しは自分の気持ちが引き寄せていると考えればよいのではないでしょうか?
春彼岸 さいごに
私も、諸事情でここのところなかなかお彼岸やお盆にお参りに行けてません。
お参りの時にお墓をきれいにしたいという思いがあるので、なんとか時間を作りたいとは思っています。
時期はづれても行きたいと思います。
お墓参りをしたから、どう、というのはないのですが、やはり、気分はよくなりますね(^^)
やることをやったみたいな・・・
そして、お参りしては、亡くなった両親に思いをはせます・・・
行けない時は、しかたないので自宅のお位牌に手をあわせ、せめてもと、それらをきれいにします。
できることをすればよいと思いますよ(^^)。
☆他のお彼岸関係の記事もご覧くださいね